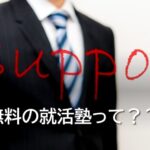【本記事で学べること】
・OBOG訪問って?その目的やメリット
・OB訪問相手がいないときの探し方の選択肢
・OB訪問アプリやメールの活用方法
・失礼にならないマナーと訪問後の対応方法
- 2025-4-21
- 2025-4-22
- 就活塾NAVIコラム
- オンライン就活, 企業研究, 就活マナー
OB・OG訪問とは、企業で働く先輩社会人からリアルな声を聞く手段のひとつです。しかし、いざ始めようとしても「志望企業にOB・OGがいないときどうやって探すのか分からない」「OBじゃない他大学の人にメールしてもいいのか不安」「そもそも社会人と会うのが不安…」といった悩みを抱える学生も少なくありません。
OB訪問をしないで内定を得ることは可能ですが、面接で説得力を持たせるための準備が必要になり、またミスマッチを防ぐ意味でもOB訪問は積極的にやることをおすすめします。
OB訪問のやり方は一つではなく、アプリやオンラインの活用、企業に直接メールを送る方法など、選択肢は広がっています。たとえ身近に訪問できる先輩がいない場合でも、工夫と行動次第で有意義な出会いや情報にたどり着けるのです。
この記事では、OB訪問の基本から、相手がいないときの探し方、アプリやメールの使い方、オンラインでの実施方法、さらには「うざい」と思われないマナーまで、幅広く解説します。自分に合ったスタイルでOB訪問を取り入れ、納得のいく就活を進めていきましょう。
※当記事にはPRが含まれています
OB訪問の希望先にOB・OGがいないときどうやって探す?
【本章のポイント】
・OB・OG訪問とは?目的とメリットを確認
・どうやってOB・OGを探すかの基本ルート
・アプリで簡単に探せる時代
・OB訪問相手をアプリで探すメリット
・OB訪問アプリはどれが使いやすい?おすすめは?
OB・OG訪問とは?目的とメリットを確認
OB・OG訪問とは、企業で働く先輩社会人に直接話を聞く就職活動の手段です。主に同じ大学や学部の卒業生にアポイントを取り、仕事の実情や社内の雰囲気、キャリアの歩み方などについて質問します。こうした取り組みは、自分に合った職場を見つけるための重要な情報源として活用されています。
特にOB・OG訪問のメリットは、企業の公式サイトやパンフレットだけでは得られない「リアルな声」を聞ける点にあります。たとえば、「実際の残業時間」や「職場の人間関係」、「評価制度の納得感」など、働いている人だからこそ語れる話は就活生にとって非常に貴重です。こうした情報は、ミスマッチによる早期離職を防ぐための判断材料にもなります。
また、OB訪問を通じて自身の志望動機や自己PRに磨きをかけることも可能です。実際に話を聞いた内容を取り入れながら志望理由を構築すると、説得力が増し、面接の際にも自信を持って話せるようになります。
ただし、OB訪問は選考の一部ではないため、訪問したからといって必ず内定に近づくというものではありません。あくまで情報収集や企業理解の一環として捉えることが大切です。そのうえで、感謝の気持ちを忘れず丁寧な対応を心がけることで、社会人としての第一歩をスムーズに踏み出す準備にもつながります。

どうやってOB・OGを探すかの基本ルート
OB・OG訪問をしたいと思っても、誰にどうやって連絡を取ればいいか迷う人は少なくありません。OB訪問には、いくつかの基本的なルートが存在しており、それぞれの特徴を解説します。
最も代表的なルートは、大学のキャリアセンターを通じて探す方法です。多くの大学では、卒業生の進路や連絡先を記録しており、希望する企業に在籍している先輩の情報を紹介してもらえることがあります。ただし、個人情報保護の観点から、事前の申請や目的の明確化が必要な場合もあるため、早めに確認しておくと安心です。
次に頼れるのは、ゼミやサークル、アルバイトなどで関わりのある先輩や友人の紹介です。このような人づての紹介は、比較的カジュアルにコンタクトが取りやすく、信頼関係も築きやすい点が強みです。また、紹介者がすでに社会人との信頼関係を築いている場合、話を聞いてもらえる確率も高まります。
一方で、企業の説明会や就活イベントに参加することで、社員の方と直接つながるという方法もあります。名刺をもらった場合には、後日メールでOB訪問の依頼をしてみましょう。ただし、企業によっては個別訪問を受け付けていない場合もあるため、対応の可否は事前に確認しておくことが必要です。またあとで詳しく解説しますが、アプリで探す方法もあります。
このように、OB訪問の基本的な探し方には複数のルートがあります。自分に合った方法を選び、丁寧な連絡や誠実な対応を心がけることで、訪問のチャンスを広げることができるでしょう。
アプリで簡単に探せる時代
これまでOB・OG訪問は「ツテがある人だけの特権」と思われがちでしたが、現在では専用のアプリを活用することで、誰でも手軽に社会人とつながることが可能になりました。こうしたアプリの普及によって、OB訪問のハードルは大きく下がり、地方大学の学生や知り合いが少ない人でも平等にチャンスを得られるようになっています。
代表的なOB訪問アプリとしては「Matcher(マッチャー)」や「ビズリーチ・キャンパス」などが挙げられます。これらは、気になる社会人を見つけたら、ボタンひとつで訪問依頼が可能という手軽さが魅力です。また、アプリでは実名だったり身元確認された社会人が登録されている点も魅力的な安心材料です。事前にプロフィールをよく読み、相手との相性を見極めたうえで連絡すれば、有意義なOB訪問が実現します。
興味のある企業の社員に会って、様々な話を聞けるというのは、学生のうちだからできる特権です。是非積極的に活用し、納得できるキャリア選びをしてください。
OB訪問相手をアプリで探すメリット
OB訪問の相手をアプリで探す方法には、従来の方法にはない多くの利点があります。特に「どの社会人に会えばいいのかわからない」「自分の大学にOBがいない」といった悩みを抱える就活生にとって、アプリは非常に有効な手段となります。ここでは、アプリを使ってOB訪問相手を探す主なメリットを詳しく解説します。
まず挙げられるのが、選択肢の広さです。アプリを利用することで、所属大学にとらわれず全国の多様な業界・企業で働く社会人と繋がることができます。所属大学の垣根を取り払い、様々なバックグラウンドを持つ社会人と出会えるため、より広い視野で情報を得ることが可能です。業種・職種だけでなく、共通の趣味やキャリア志向を持つ人を絞り込む機能があるアプリも多く、より“自分に合った”OB訪問ができます。
次に、効率的な情報収集ができることもポイントです。多くのアプリでは、社会人の所属企業や業界、経歴といった詳細なプロフィールが掲載されているため、話を聞く前にある程度の情報を把握できます。また、過去に訪問した学生による口コミや評価を参考にできるケースもあり、「この人に話を聞いてみたい」と思えるかどうかを判断しやすい仕組みになっています。
さらに、手軽さと利便性も大きな魅力です。アプリ内のチャット機能を使えば、フォーマルなメールのような堅苦しい文面を用意せずとも、気軽に連絡を取ることができます。中には、アプリ上で相手の空き時間を確認して面談の日程調整ができるサービスもあり、スムーズに予定を決めることが可能です。オンライン対応のOB訪問であれば、地理的な制限もなくなり、地方に住む学生でも気軽に都市部の社会人に話を聞けるようになります。
また、新しい出会いや思わぬ気づきがあることも見逃せません。アプリ上でたまたま目に留まった社会人から、新しい業界への興味が芽生えることもあります。さらに、一部のアプリにはスカウト機能が搭載されており、社会人や企業側からアプローチを受けることも。就活の可能性を広げるきっかけになるでしょう。
最後に、安心して利用できる環境が整っていることもアプリの強みです。多くのサービスが実名制・本人確認を徹底しており、トラブル防止のための監視体制も充実しています。安心感を持って社会人とのやり取りができる点は、特に初めてOB訪問をする学生にとって重要な要素です。
ただし、アプリによっては登録者の傾向や機能に差があるため、複数を比較して自分の目的に合ったものを選ぶようにしましょう。単にエージェントによる学生の情報収集目的のサービスもあり、気を付けたいところです。
ただし上手に使えば、OB訪問アプリはあなたの就活を大きく後押ししてくれる頼もしいツールになります。
OB訪問アプリはどれが使いやすい?おすすめは?
OB訪問をスムーズに進めるためには、自分に合ったアプリを選ぶことが重要です。現在、多くの学生が利用しているOB訪問アプリの中でも、特に支持を集めているのが「Matcher(マッチャー)」と「ビズリーチ・キャンパス」です。基本的にはこの2つを抑えていけば間違いないでしょう。ここでは、それぞれの特徴やおすすめポイントを詳しくご紹介します。
大学に関係なく使える|Matcher(マッチャー)
Matcherは、登録者数約42,000人以上を誇る、国内最大級のOB訪問アプリです。最大の特徴は、出身大学に関係なく誰でも社会人と繋がれる点にあります。OBが自分の大学にいない場合でも、興味のある企業の社員に直接アプローチできるため、地方大学や中堅大学の学生にも非常に人気です。
操作は非常にシンプルで、気になる社会人に「就活相談に乗ってほしい」と依頼をするスタイルで、マッチング率は70%以上。社会人側も気軽に参加しているため、ハードルが低く、カジュアルに話ができるのが魅力です。
社会人は実名登録で、350,000件を越えるレビューを確認して選ぶことができ、24時間365日の監視体制なので安心、安全なサービスといえるでしょう。ワンクリックで希望に合うOB・OG訪問が実現します。
また、Matcherでは就活相談だけでなく、自己分析やES添削、面接練習といった就活全般のサポートも受けられます。企業からスカウトが届く機能もあるので、「OB訪問 × スカウト」で効率的に就活を進めたい人には特におすすめのアプリです。
有力大学の学生向け|ビズリーチ・キャンパス
ビズリーチ・キャンパスは、特定の大学に在籍する学生向けに設計されたOB訪問アプリで、現在国内81大学の学生が対象です。登録している社会人は10万人を超え、大手企業や人気企業に勤める先輩が多いのが特徴です。
このアプリでは、自分の大学の卒業生とマッチングする形式が中心で、同じ学部やサークル出身の先輩に出会えることもあります。共通点があるため、親しみやすく、OB訪問が初めての学生でも安心して会話ができる環境が整っています。
さらに、アプリ内ではOBとの交流会や企業セミナーが開催されており、情報収集だけでなく、選考に直結するイベントに参加できるチャンスもあります。スカウト機能や自己分析ツールも充実しており、就活の総合サポートとして活用したい方に向いています。
安心・安全面でも配慮されており、OB/OGには「企業公認」と「ボランティア」の2種類があり、ボランティアのOB/OGは原則としてオンライン訪問のみに制限されています。これにより、オフラインでの予期せぬトラブルを防いでいる点も安心材料です。
先輩の就職体験記「いつ・何をして・何に悩んだのか」が読めるのもメリットです。
大手企業や人気企業を目指す学生にとって、情報や人脈を得る手段として非常に有効なアプリだと言えるでしょう。自分の大学が対象かどうかを確認し、該当しているのであれば是非活用してみてください。
このように、Matcherは「大学に関係なく幅広く社会人から話を聞きたい人」に、ビズリーチ・キャンパスは「対象の大学に在籍していて、大手や人気企業の社会人に話を聞きたい人」に向いています。自分の就活スタイルに合わせて、うまく活用していくのが成功のカギです。
OB訪問の希望先にOB・OGがいない場合の選択肢
【本章のポイント】
・OB訪問の希望先にOB・OGがいない場合の選択肢
・同じ大学のOBじゃなく、他大学からでも
・企業に直接メールする方法
・うざいと思われないマナーとは
・OB訪問をしないで内定、やらなかった人の例
・相手がいないなら行動あるのみ
同じ大学のOBじゃなく、他大学からでも
OB・OG訪問と聞くと「同じ大学の卒業生」に話を聞くイメージが強いかもしれませんが、実際には他大学の社会人に訪問することも十分に可能です。とくに近年では、OBに限らず「業界の先輩」として幅広く情報を得ようとする学生が増えており、その際にアプリやメールの活用が有効な手段となります。
まず前提として、他大学出身の社会人であっても、就活生の相談に乗ってくれる方は多くいます。その場合、きちんとした目的と礼儀をもって連絡すれば、快く対応してもらえる可能性は十分にあります。特に企業の社員紹介ページやSNS、講演会、セミナーなどで名前を知った場合には、そこからメールでアプローチするケースが一般的です。
このときのメールは、連絡のきっかけや理由を簡潔かつ丁寧にまとめることが大切です。それにより、相手の信頼を得やすくなります。
ただし、他大学の学生がいきなりメールを送る場合は、誤解を与えないように注意が必要です。業務中に突然のメールが届くことに対して、驚かれることもあるため、必ず件名に「OB訪問のお願い」などの意図を記載し、失礼のない文面を心がけましょう。
また、返事が来ないからといって何度も催促するのは避けた方が良いでしょう。忙しい社会人であれば、対応できないこともあります。そのような場合は、次の候補者に切り替えるなど、柔軟な姿勢を保つことが重要です。
このように、他大学の社会人に対しても、メールを通じて丁寧に依頼すれば、有意義な情報を得られる可能性があります。大学の枠にとらわれず、広い視野でアプローチしてみましょう。
企業に直接メールする方法
OB・OG訪問の相手が見つからないとき、企業に直接メールを送って相談するという方法も選択肢の一つです。最近では企業側も就活生からの問い合わせに一定の理解を示している場合が多く、丁寧な依頼であればしっかりと対応してもらえることがあります。
まず最初にやるべきなのは、企業の公式サイトをチェックすることです。採用情報ページに「OB・OG訪問希望の方へ」といった項目がある場合があり、その指示に従って連絡します。特に指定がない場合は、問い合わせフォームや新卒採用窓口のメールアドレスを利用します。
メールを送る際のポイントは3つあります。1つ目は、件名を明確にすること。「OB訪問希望(◯◯大学・氏名)」のように、内容が一目で分かるようにします。2つ目は、本文に自己紹介、連絡の経緯、訪問の目的を端的に書くこと。そして3つ目は、訪問方法の希望(オンライン可否)や候補日時を記載し、相手の負担を最小限にする配慮を加えることです。
例えば「貴社での働き方や社員の方のキャリアについて詳しく伺いたく、ご連絡差し上げました。オンラインでも構いませんので、15分程度お時間をいただけないでしょうか。」といった表現が効果的です。
ただし、すべての企業がOB訪問を受け入れているわけではありません。断られた場合でもマナーを守ってお礼を伝え、無理に食い下がらないようにしましょう。このようなやり取り一つひとつが、社会人としての姿勢を問われる場でもあります。
企業への直接メールは勇気がいるかもしれませんが、誠意を込めて送ることで新たな出会いや情報収集につながる可能性があります。行動を起こすことが、結果につながる第一歩となるのです。
うざいと思われないマナーとは
OB訪問では、社会人の貴重な時間を割いてもらうことになるため、「うざい」「失礼だ」と思われないよう、基本的なマナーを守ることが不可欠です。せっかくの機会を無駄にしないためにも、訪問前から訪問後までの一連の流れに配慮が求められます。
まず大切なのは、訪問依頼時の態度です。連絡の際には、自分の立場をわきまえ、相手が忙しい社会人であることを忘れないようにしましょう。突然の電話や唐突なメッセージは避け、丁寧なメールで依頼するのが基本です。特に初対面の相手に対しては、依頼文に「ご多忙のところ恐縮ですが」や「お手すきの際にご確認いただけますと幸いです」といった一文を添えることで印象が変わります。
当日の訪問では、服装や言葉遣い、態度に気を配りましょう。基本はリクルートスーツ、挨拶は明るく、相手の話をしっかり聞く姿勢が大切です。質問を用意しておくのは望ましいですが、一方的に質問攻めにするのではなく、会話のキャッチボールを意識しましょう。
また、訪問時間を守ることもマナーの一部です。遅刻はもちろん厳禁ですが、終了時間を大幅に過ぎて話を続けるのも避けましょう。予定時間が近づいたら「そろそろお時間大丈夫でしょうか」と相手を気遣う言葉を添えると好印象です。
訪問後には必ずお礼のメールを送りましょう。メールには、訪問のお礼だけでなく、「本日伺ったお話で最も印象に残ったこと」や「今後の就活にどう活かす予定か」などを添えると、丁寧さが伝わります。
このように、ちょっとした配慮の積み重ねが、OB訪問を成功に導きます。社会人としての基本的な礼儀を意識することで、相手に不快感を与えることなく、信頼を得ることができるのです。
OB訪問をしないで内定、やらなかった人の例
OB訪問を「やらなかった」「できなかった」という就活生も一定数いますが、そのことが必ずしも不利に働いたとは限りません。実際にOB訪問をせずに内定を得た人たちは、別のアプローチで情報収集や自己分析を行い、自分なりの対策を徹底していたことが特徴です。
たとえば、ある学生は地方大学に通っていたため、志望企業にOBがいなかったものの、企業ホームページや口コミサイト、YouTubeでの社員インタビュー動画などを活用して徹底的に企業研究を行いました。そのうえで、説明会やインターンに積極的に参加し、採用担当者との接点を自ら作り出していました。
他にも、逆求人サイトや就活エージェントを使って企業と直接つながり、OB訪問を介さずに企業理解を深めた例もあります。このようなサービスでは、面談や模擬面接を通じて社員と話す機会が設けられているため、実質的にはOB訪問と同様の効果を得られたりします。
もちろん、OB訪問は企業のリアルな情報を得られる有効な手段ではありますが、それだけが唯一の方法ではありません。むしろ、自分に合った方法を選び、主体的に動いたかどうかが、就活の成功に直結するポイントです。
ただし、OB訪問をしない場合は、他の手段で「なぜこの企業を選んだのか」「どんな情報を得たのか」という根拠をしっかり言語化しておく必要があります。そうしなければ、面接で説得力を持たせることが難しくなるからです。

OB訪問をやらなかったこと自体は致命的な問題ではありませんが、その分、他の努力をしっかり積み重ねていくことが重要です。自分の環境や状況に応じた就活スタイルを確立できれば、内定を勝ち取ることは十分に可能です。
相手がいないなら行動あるのみ
「OB訪問をしたいけど、相手がいない…」と悩んで立ち止まってしまう就活生は少なくありません。しかし、相手がいない状況で悩み続けても、前には進めません。OB訪問の成功は、情報量や人脈ではなく、自ら行動できるかどうかにかかっています。
現在は、インターネットやSNS、専用アプリなど、社会人とつながるための手段が多く存在します。前述のOB訪問アプリのほかにも、FacebookやLinkedInを使えば、志望企業の社員を見つけ、メッセージでコンタクトを取ることが可能です。企業説明会やインターンシップで知り合った社員に後日アプローチするのも一つの手段です。
重要なのは、「完璧な状況」になるのを待たないことです。最初の一歩を踏み出すことで、次の選択肢が見えてきます。メールを送る、イベントに参加する、SNSで調べる、どれも小さな行動ですが、結果的に大きな成果につながります。
行動を起こすことに不安がある人もいるかもしれませんが、相手も一人の社会人であり、学生の真摯な姿勢に応じてくれるケースも多いのです。勇気を出して一歩踏み出してみましょう。
OB訪問先がいないときはどうやって探すかのまとめ
就職活動では、思い通りにいかないことや不安に感じる瞬間が何度も訪れます。OB訪問についても色々不安はあるでしょう。
しかし、大切なのは、自分で考え、行動し続けることです。アプリやオンラインの活用、他大学の先輩へのアプローチ、企業への直接連絡など、できることはたくさんあります。臆せず一歩を踏み出してみてください。小さな行動の積み重ねが、将来につながる大きなチャンスに変わります。
あなたの就職活動が、自分にとって納得のいく選択につながるよう、心から応援しています。焦らず、あきらめず、自分のペースで前に進んでいきましょう。
ポイント:
・OB・OG訪問は企業理解を深める情報収集手段
・キャリアセンターで卒業生の情報を確認できる
・ゼミやサークルの先輩に紹介を頼む方法もある
・説明会や就活イベントで社員に直接アプローチできる
・OB訪問アプリを使えば大学に関係なく社会人に会える
・Matcherは大学不問で利用できマッチング率も高い
・ビズリーチ・キャンパスは有力大学の学生に特化している
・アプリにはプロフィールや口コミ機能があり選びやすい
・オンライン対応で地方からでも気軽に参加できる
・アプリにはスカウト機能やイベント情報も含まれる
・他大学出身者にも丁寧なメールでアプローチが可能
・社員に直接メールを送って訪問を依頼する手もある
・OB訪問をしなくても内定を得る手段はあるが、対策は必要
・最も大切なのは行動し続ける姿勢を持つこと
この記事の著者
就活塾NAVI編集部
就活塾NAVI編集部は、独自取材や受講者の声をもとに、就活塾の比較・評判・選び方をわかりやすく、丁寧に紹介しています。業界動向にも敏感に対応し、全国の学生の“安心できる就活”を全力でサポート。気軽に読んで参考にしてください。
この著者の最新の記事
-
- 2025-11-27
- 就活塾あれこれ
地方国立大から食品メーカー内定へ|情報不足から逆転した就活塾体験談
-
- 2025-10-27
- 就活塾あれこれ
キャリアセンターだけだと不安…就活塾で内定をつかんだ実例
-
- 2025-9-28
- 就活塾あれこれ
【実例】夏インターン全落ちでも大逆転!就活塾で内定へ
-
- 2025-8-30
- 就活塾あれこれ
ESが通らなかった学生が就活塾で変わった“自己PR改善術”
関連記事
-
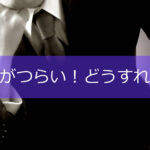
- 2017-7-13
- 就活塾NAVIコラム
【就活生必見】就活がつらいとき、どうすればいいのか?
-

- 2017-6-22
- 就活塾NAVIコラム
【徹底解説】就活において英語はどこまで必要なのか?
-
- 2024-1-19
- 就活塾NAVIコラム
AI監視型Webテスト:不正リスクと効率的な対策について
-

- 2017-6-29
- 就活塾NAVIコラム
必見!! 就活における留年の理由の伝え方は?【例あり】
-

- 2018-9-28
- 就活塾NAVIコラム
内定者懇親会、内定式で失敗しないためのマナー
-

- 2017-9-14
- 就活塾NAVIコラム
就活に学歴って関係あるの?学歴フィルターって?企業のホンネを教えて!